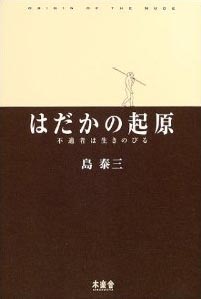記憶にあるのは、左端のチンパンジーみたいなサルの絵から、右端のいかにも人間らしいヒトの図にはさまれた、四つか五つかのサルともヒトともつ かない奇妙な行列です。左端のサルは背が低くて背中を丸め、両手を地面の近くまで垂らしていました。膝が曲がって、もちろん毛むくじゃらの体で す。サルだから毛皮をまとっていたことに疑いはありません。右端はとにかくヒトですから、丈は一番高くて背筋を伸ばしており、丸ハダカでした。こ の二つにはさまれた他の連中は、右にいくほど背が高くなって、膝も伸びていきます。それに合わせて、毛むくじゃらの程度も減っていくんです。どん な説明の言葉がついていたのか、そこまでは思い出せません。
そろそろ「ハダカ」の話題に入るつもりなので、教科書で紹介した(96ページ)島 泰三さんの『はだかの起源 不適者は生きのびる』木楽舎(平成 16年)を読み直したんです。そしたら、「出アフリカ」でドキッとし ました。この言葉を人類の移動に使ったのは、英国人のクリストファー・ストリ ンガー(Christopher Stringer)が最初です。だから当然それは英語の「Out of Africa(アウト・オブ・アフリカ)」です。島さんの本には、これは邦題「愛と哀しみの果て」として映画化されて大ヒットした小説、『アウト・オブ・ アフリカ』から採られている、と書いてあったのです。「そうだったのか!」と、あわててストリンガーの著作を調べてみたら、C・ ストリンガーと R・マッキーの共著で『出アフリカ記 人類の起源(African Exodus : The Origins of Modern Humanity, 1996)』(岩波書店、平成13年)という本がありました。Exodus(エクサダス)とは旧 約聖書の「出エジプト記」のことですから、僕の説明も、ま んざらではなかったようです。
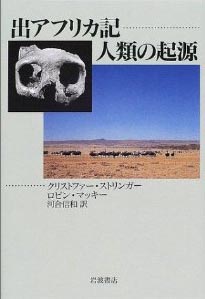 哺乳動物の体表の話に進もうとして、また寄り道してしまいました。ごめんなさい。で、体表(ハダカ)
の話なら、ぜひ島さんの『はだかの起源』を
読んでいただきたいのですけど、たぶん無理なお願いでしょう。そこで、教科書のさっきの箇所のあたりと少し重複することをお許し願って、島さんの
説をごく簡単に紹介します。
哺乳動物の体表の話に進もうとして、また寄り道してしまいました。ごめんなさい。で、体表(ハダカ)
の話なら、ぜひ島さんの『はだかの起源』を
読んでいただきたいのですけど、たぶん無理なお願いでしょう。そこで、教科書のさっきの箇所のあたりと少し重複することをお許し願って、島さんの
説をごく簡単に紹介します。衣類と家屋をもたない野生動物にとって、毛皮は、体の温度と湿度を保つための必需品です。体温は、上がりすぎても下がりすぎても致命的です。乾 燥したら、干からびて死ぬだけです。彼らが暴風雨のさなかでも活動できるのは、まさに毛皮の防水性と保温性のおかげなのです。だから毛皮を失った 動物はとても稀です。現生している、その稀なグループは三つあります。第一はゾウのような巨大な動物で、中小の動物に比べて体積に対する表面積が 少ないのが特徴です。もろもろの活動によってたまる体内の熱を逃がしにくいから、断熱性の毛皮などはないほうがよろしい。第二はクジラのように水 中の生活者で、けっして陸には上がりません。水中では毛と毛のあいだの空気が追い出されるから、断熱の役に立ちません。だから無用な毛を捨てたハ ダカになって、代わりに厚い皮下脂肪を蓄えるのです。その証拠に、陸上でも活動するアザラシなどは毛皮を残しています。
第三は、グループともよびにくい、少数の変わった連中です。バビルーサというイノシシ、ハダカオヒキコウモリ、ハダカデバネズミ、そして「ハダ カのサル」であるヒト、わずかにこの四種です。ホントはもう一種、大型カバの先祖といわれるコビトカバ(体重は他のカバの二十分の一くらい)がい ます。けど、生きていける特殊な環境がなくなってきて、絶滅しそうです。他のカバたちは、大きくなるという進化(多様化)を遂げて、普通の環境に 適応したんでしょうね。イノシシの属する偶蹄目、コウモリの翼手目、ネズミの齧歯目(げっしもく、目とは分類上のかなり大きなくくり)、サルの霊 長目、これらはどれも、哺乳類のなかで繁栄を誇っている動物群で、種の数はとても多いのです。それなのにハダカなのは、それぞれの目に属する、た だ一種だけです。
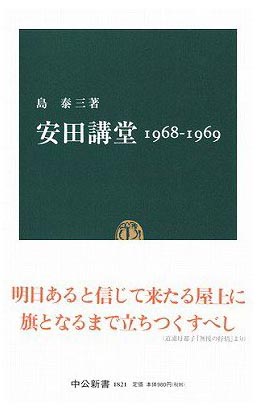 そこで島さんは、哺乳動物で毛皮がなくなるように突然変異した個体は、たとえ現れたとしてもアルフレッド・ウォレス(Alfred R.
Wallace)とチャールズ・ダーウィン(Charles R.
Darwin)が唱えた自然選択を受けて、直ちに淘汰されてしまっただろうとおっしゃいます。ハーバート・スペンサー(Herbert
Spencer)がいい出し、ダーウィンも使うようになった適者生存(survival of the
fittest、厳密には最適者生存)の原理に反するからです。たしかにコビトカバは絶滅しそうですけど、バビルーサも、ハダカオヒキコウモリも、ハダカ
デバネズミも、種と認められるほどに栄えて、いまだに生存しています。ヒトにいたっては七十億以上の個体数にまで増えています。哺乳動物の一つの
種としては最多数でしょう。(最)適者生存なんてナンセンス! 大学紛争に深く身を投じ、警視庁機動隊の放水と催涙弾を浴びながら「明日あると信
じて来る屋上に旗となるまで立ち尽くすべし」と、『安
田講堂 1968-1969』(中央公論社、平成17年)を著された島泰三さんです。ノラリ
クラリと論点をはぐらかし、理屈の綻びを言葉の綾で取り繕うダーウィンの論法など、一刀のもとに斬って捨てられます。
そこで島さんは、哺乳動物で毛皮がなくなるように突然変異した個体は、たとえ現れたとしてもアルフレッド・ウォレス(Alfred R.
Wallace)とチャールズ・ダーウィン(Charles R.
Darwin)が唱えた自然選択を受けて、直ちに淘汰されてしまっただろうとおっしゃいます。ハーバート・スペンサー(Herbert
Spencer)がいい出し、ダーウィンも使うようになった適者生存(survival of the
fittest、厳密には最適者生存)の原理に反するからです。たしかにコビトカバは絶滅しそうですけど、バビルーサも、ハダカオヒキコウモリも、ハダカ
デバネズミも、種と認められるほどに栄えて、いまだに生存しています。ヒトにいたっては七十億以上の個体数にまで増えています。哺乳動物の一つの
種としては最多数でしょう。(最)適者生存なんてナンセンス! 大学紛争に深く身を投じ、警視庁機動隊の放水と催涙弾を浴びながら「明日あると信
じて来る屋上に旗となるまで立ち尽くすべし」と、『安
田講堂 1968-1969』(中央公論社、平成17年)を著された島泰三さんです。ノラリ
クラリと論点をはぐらかし、理屈の綻びを言葉の綾で取り繕うダーウィンの論法など、一刀のもとに斬って捨てられます。その島さん、ハダカオヒキコウモリについては、とりわけ飛んでいるときの保湿と保温の方法については、全くの謎だとされています。また、バビ ルーサとコビトカバについては、森の中の沼のあたりに住むことでこの問題を解決しているらしいけれど、そういう場所は観察者を寄せ付けないので生 態がわからない、と嘆いておいででした。ハダカデバネズミは厳然とした階級社会を作っていて、労働階級のメンバーが掘って維持している穴倉の中 で、すし詰めになって湿度と体温を保っているそうです。
ここまでの大切な二点を強調しておきます。(一)、毛皮が必要な野生動物の中で、生存に不都合なハダカの状態になった種でも、その弱点をカバー できる環境を見つけたり、作り出すことができれば、生き残れます。(二)、しかしそんな環境を独占することは、よほどの運に恵まれないと不可能だ から、多数の種を抱える「目」という分類段階の中でも、せいぜい一種だけで、二種も三種もいることはありません。
ここを押さえたうえで、ヒトが数千万年前の霊長類の先祖から分岐していく過程の、どの段階でハダカになったのかを考えましょう。その答え次第 で、ネアンデルタール人もハダカだったのか否か、それが決まるはずです。参考までに、いま生きている動物の分類の中での、ヒトの肩書きを書いてお きます。霊長目、真猿亜目、狭鼻下目、ヒト上科、ヒト科、ヒト属の、種小名サピエンス、というわけです。真猿亜目には原猿亜目が並び、狭鼻下目に 対しては広鼻下目があって、ヒト科と並ぶのはテナガザル科とオランウータン科(教科書ではショウジョウ科)です。なお、オランウータン科を廃し て、ヒト科の下に、ヒト亜科とオランウータン亜科を並べるなど、このあたりは類人猿をどう考えるかで議論百出です。いま生きているサルたちだけを 考えても、これだけの段階をふんで分けていかないと、ヒトには行き着きません。そしてそのヒトが、唯一のハダカのサルなのです。