ネアンデルタール人は墨守の人類です。記憶には優れていたかもしれませんけど、創造は苦手だったようです。なぜなら、彼らの石器は十数万年にわ たって全く変化していないからです。改良の跡がないのです。石刃に似たモノを遺したシャテルペロン文化(「石刃、首飾り、顔料」の項)は、サピエ ンスの模倣でした。彼らにとって、道具の素材は石と決まっていたのです。火といえば、調理の手段としか考えなかったと思われます。
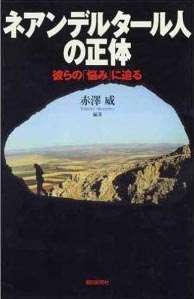 寒い時期を生き抜くためには、火の絶えない暖房用の炉辺も不可欠です。「炉なら北京原人(エレクト
ス)の時代からあったじゃないか」と思われる
かもしれません。しかし、あの化石が見つかった周口店の「遺跡」は住居跡ではありませんでした。火の燃えた跡があるとすれば自然発火の結果だ、と
いうのが現在の見解です。シリアのデデリエ洞窟やフランスのドルドーニュ地方の洞窟群、その他のネアンデルタール遺跡には「火を使った跡」こそ数
多くあるけれど、どれも暖房設備としての「常用の炉辺」の跡と判断するには無理があるようです(『ネ
アンデルタール人の正体』にある西秋良宏「1 日を推理する」、マイラ・シャクリー『ネアンデルタール人』)。
寒い時期を生き抜くためには、火の絶えない暖房用の炉辺も不可欠です。「炉なら北京原人(エレクト
ス)の時代からあったじゃないか」と思われる
かもしれません。しかし、あの化石が見つかった周口店の「遺跡」は住居跡ではありませんでした。火の燃えた跡があるとすれば自然発火の結果だ、と
いうのが現在の見解です。シリアのデデリエ洞窟やフランスのドルドーニュ地方の洞窟群、その他のネアンデルタール遺跡には「火を使った跡」こそ数
多くあるけれど、どれも暖房設備としての「常用の炉辺」の跡と判断するには無理があるようです(『ネ
アンデルタール人の正体』にある西秋良宏「1 日を推理する」、マイラ・シャクリー『ネアンデルタール人』)。この『ネアンデルタール人の正体』には、彼らの生活の一部を描いた絵が四枚、ジオラマ(絵に描いた背景の手前に数体の人形を配して当時の生活を 想像させる仕掛け)が二つ、写真で紹介されています。絵の一枚はフランス、ジオラマの一方はアメリカ、そのほかは日本にあります。この六つの作品 には、合わせて二十五体の大人のネアンデルタール人が登場していますけれど、基本は全てハダカです。毛深いのもいるけど、ハダカなのです。裂いた 毛皮を腰に巻いたり、肩にかけたり、背にはおったり、そう表現されている人物がある一方で、全裸の大人も六体ありました。そのほかに、国外の個人 画と個人像が七つあります。でも、ケモノとして表わされているのは、ブールが注文したクプカの絵(「多様性と混血論」の項)だけでした。こういう 絵やジオラマを監修なさる学者さんたちは、きっと真夏の情景がお好きなんでしょうね!
この七つの中には、髭を剃られ、頭髪は七・三分け、背広にネクタイという姿のネアンデルタール人像があります。『シャニダール洞窟の謎』の原書 (「ジーン・アウルを動かした花粉」の項)が出るよりもずっと前の昭和十四年、カールトン・クーン(Carleton S. Coon)という人類学者が発表した論文に、「ネアンデルタール人が、髭を剃り、髪を整えてニューヨークの地下鉄に乗っていたら、だれも気にしないだろ う」という記述があったからです。その論文の趣旨は、現代白色人種の先祖はネアンデルタール人だ、というものです。その根底には、ヨーロッパ人 (コーカサス人種)が最も早くサピエンスの段階に到達した、という人種偏見につながる「ヒトの多地域進化説」があるんです。現在この説は、ミトコ ンドリアDNAを利用したウィルソン・グループの研究(「ハダカになった人類」の項。報告者は、キャン、ストーンキング、ウィルソンの三人)が決 定打になった「ヒトのアフリカ起源説」によって、完全に取って代わられています。なお、「頭髪を七・三分け」にした像は平成八年の作で、「多地域 進化説」を支持するための展示ではありません。
このキャン(Rebecca L. Cann)らの報告(昭和62年)は、発表された当初こそ、化石をもとにして人類の進化を論ずる「正統的な」人類学者から猛反撃を受けましたけれど、時代 が平成に入ってしばらく経つと、「アフリカ起源説」の正当性はだれの目にも明らかになってきました。いまの世界に生きるすべての人間は、たぶん三 十万年近く前に起源をもつであろう、エチオピア高原に住んでいたヘルト人に代表される肌の黒い人類の子孫なのです。その頃にはすでに霊長目の中の 唯一のハダカ種になっていて、誤嚥(ごえん)の危険性とは隣り合わせながら、アニ(兄)とアネ(姉)、ハート(heart)とハード(hard) などを区別して喋れる発音能力をもっていたのでしょう。この能力が、それまでの人類と比べれば格段に高い会話力を生み出し、そしてそれが、もとも と素地のあった前頭葉の発達を推し進めたのだと思います。
「ハダカの周辺」の項で、ヒトはチンパンジーに比べると、のどの下の部分が下に広がって、口 から気管までの筋肉を操るための神経が発達したこと を書きました。でも、ネアンデルタール人には触れませんでしたね。直立二足歩行することで変わってくる「のど」の構造では、彼らもヒトに近いはず です。けれどその声帯の位置は、ヒトよりもかなり低いのです。のどは長いのに声帯が下のほうにあったら、吐く息を使って声帯を震わせても、舌や
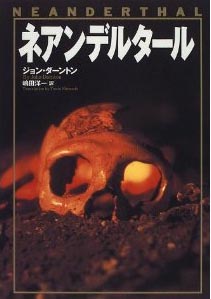 唇
に届くまでにはその振動が弱くなって、ヒトのように発声するのは無理だろうといわれています。ジョ
ン・ダーントン(John Darnton)の『ネアンデルタール(Neanderthal、1996)』ソ
ニー・マガジンズ(平成8年)のネアンデルタール人は声を出せません。
ジーン・アウルの『ケーヴ・ベアの一族』は、複雑な音を使わない乏しい会話しかできずに、コミュニケーションの多くを身振りに頼っておりました。
唇
に届くまでにはその振動が弱くなって、ヒトのように発声するのは無理だろうといわれています。ジョ
ン・ダーントン(John Darnton)の『ネアンデルタール(Neanderthal、1996)』ソ
ニー・マガジンズ(平成8年)のネアンデルタール人は声を出せません。
ジーン・アウルの『ケーヴ・ベアの一族』は、複雑な音を使わない乏しい会話しかできずに、コミュニケーションの多くを身振りに頼っておりました。ヒトのハダカ化、のどの変形、声帯の位置の移動、前頭葉の発達、これらがどういう遺伝子の変化によって、どういう順序で、どのくらいの時間をか けて達成されたかは想像もつきません。僕にできるのは、ウマの蹄が完成するのにかかった時間に比べれば、アッという間のことだっただろう、と繰り 返すことだけです。
ダーントンの描くネアンデルタール人も、ケーブ・ベアの一族と同じように、ヒトよりは毛深いけれどハダカでした。ダーントンは雪深いパミール高 原にいまも生きている架空のネアンデルタール人を、それほど大きくはないけれど、かなりの体重がありそうで頑丈な体格だ、と表現しています。彼ら が身につけているのは、粗末な仕立ての毛皮の貫頭衣と脛当て、原始的なカンジキだけです。だから現代人である小説のヒロインは、その体を胴体の中 央部分と胸部が大きく、二の腕の筋肉はヒトの二倍くらいあって、長いたてがみのような頭髪が首の辺りにかかっている、と見て取ることができまし た。頑丈でずんぐりした体型は、学者たちが著した解説書にも書いてあって、それを寒冷な気候に適応した結果だとしています。
学者たちは、この「寒冷適応」した体型を説明するとき、エスキモー(カナダ側のイヌイット、アラスカとロシアのユピク、グリーンランドのイヌ イット系のカラーリット、これらの総称)の人たちを例に出します。でも、彼らは疑いなくホモ・サピエンスで、全身を覆うことのできる「仕立てのい い」衣服や、防寒テントをもった上での適応です。「縫い針」を知らないハダカの人類が、身体そのもので自然環境に適応しているなら、「ずんぐりし た体型」だけでは生き延びていけないでしょう。何に追いつめられたにしても、寒冷な場所を避難地に選ぶはずはありません。野生動物だった頃からの 毛皮をまとっているからこそ、暑い季節には綿毛をへらして、昼間はできるだけ日陰に入って、ついに寒い気候の土地へも進出できたのだと思います。
ネアンデルタール人が、「貫頭衣と脛当て」しかもっていなかったのか、それさえもっていなかったのかは不明です。前歯がひどく磨り減っているこ とから、彼らは歯を使って皮をなめした、という記述をよく見ます。けれど皮なめしは、前歯をすり減らす可能性の一つではあっても、すべてではあり ません。彼らが毛皮を使っていたという確証はないのです。とにかく彼らは、自分の体で耐えられる限界までの北進に挑戦して、それ以上は諦めまし た。先祖が耐えられると判断した土地でも、寒さが増せば南の地方に退避すればよかった――ある時期までは。その時期とは、南方に、優れた道具とそ れを作る知恵をもったホモ・サピエンスが数を増すまで、です。六万年くらい前だとパレスチナ地方のケバラ洞窟から、初期サピエンスの技術を真似た シャテルペロン文化の遺物と共に、ネアンデルタール人の骨が出てきます。けれど四万年から三万年前になると、もうそこはサピエンスの版図になって いて、ネアンデルタール人はカフカス山脈の北斜面から黒海の北岸までしか南下できなくなりました。そして人口を減らしながらイベリア半島の南端ま で後退して、ウルム氷期の最寒期に当たる二万八千年か二万四千年前に消えていったようです。
これをサピエンスの側から見ると、やっとパレスチナ地方にまで進出したのは、およそ十万年前のことで、エチオピア高地で誕生してから十万年以上 経ってからです。それは、南アフリカで顔料工場が営まれていた時代でもあります。ケバラ洞窟から数十キロしか離れていないカフゼーの洞窟では、確 かなところ十二万から九万年前のサピエンスの遺骨が見つかっています。しかし六万年前になると、そのあたりは再びネアンデルタールの土地になって いたわけですから、十分な数のネアンデルタール人がいるあいだは、その時期のサピエンスの実力では、そこから先へ進めなかったんです。ケモノであ るネアンデルタール人にだって、それくらいの知恵と力があったのですね。
彼らが、サピエンスの文化に憧れる気持をもっていただけでも、素晴らしいことだと思います。貝殻ビーズの首飾りも、もしかしたら本当に作ろうと したのかもしれません。しかし、それは毛むくじゃらの首にかけても映えないし、そうする意義もわからなかったでしょう。だから「ネアンデルタール 人の首飾り」は、アルスアガの願望だったといったのです。それからシャニダール四号の周りの花粉、昨今、あれは地形のせいで、偶然にあの場所に流 れ込んだか吹き寄せられたのだろう、という見解が優勢です。その理由は、他に類例が見つからないからです。「埋葬」も、彼らの抽象能力を考える と、死者を悼むためではなく、仲間の体が肉食獣に貪り食われないようにするためだ、とみなされています。
余談ながら、炉跡についてマイラ・シャクリーの本(「学問と小説」の項)を調べているとき、 彼女がネアンデルタール人をケモノでもいいと考えて いる記述を見つけました。あの本を執筆していた頃のシャクリーは、ネアンデルタール人が、ロッキー山中の「サスカッチ」やヒマラヤの「イエ ティ」、モンゴルの「アルマ」のような「毛むくじゃらの霊長類(一括して『ビッグフット』とよばれることもある)」として生き残っている、と期待 していたようです。実際、彼女はアルマを求めてモンゴルへ長期に探索に出かけたのですから。しかし、ネアンデルタール人がビッグフットの先祖であ るのなら、彼らも当然ケモノのはずです。これは、ネアンデルタール遺跡の炉跡にこだわることと矛盾します。
ところで、ネアンデルターレンシスとサピエンスとのあいだで混血があったのか否か、という問題が残っていましたね。遺伝子のレベルでは、その可 能性もあり得るということでした(「なぜ混血が問題なのか」、「混血論の続き」)。僕の意見は「否」です。「混血」という言葉を、『ケーブ・ベア の一族』のダルクやウラのような子供が生まれるという、ごく狭い意味に限ったとしても、やっぱり「否」です。子供が生まれるためには、身ごもった 女性が産む気にならないといけません。あの小説では、ネアンデルタール人もハダカの人類だという設定でした。そのうえダルクの場合は、サピエンス の女(エイラ)がその相手を含むネアンデルタールの一族に養育されていましたから、読者はあまり不自然さを感じないですんだのです。
立場が逆になるウラの場合は、詳細が書かれていないし無意識に現代と混同してしまうから、作者の術中に陥ってしまうのだと思います。僕はネアン デルターレンシスを、男女を問わずサピエンスよりも筋骨のたくましい、ケモノだと考えています。彼らの骨から推定される筋肉の強さは、ダーントン の『ネアンデルタール』に描かれているとおりで、それは子供にも当てはまる遺伝的な資質でしょう。ウラの母親に挑んだサピエンスの男は、首の骨を 折られずにすんだら幸いだと思うべきです。そういう次第で、化石に跡を遺すほどの頻度で混血児が生まれたとは思えません。だから、「否」なので す。そもそも『ケーブ・ベアの一族』が書かれたのは、キャンらの論文(1987)の七年以上も前です。当時は、ネアンデルタール人が初期サピエン スに吸収されて現代人に変わってきた、という考えが主流だったのです。
その見方が変わって、ネアンデルタール人は滅亡したのだ、という考えに傾いていったきっかけは、キャンらの論文の発表でしょう。じゃぁ、どうい うふうに滅んでいったのか? 僕はまだ、サピエンスとの戦争説に否定的な本にしか出あっていません。否定の理由は、戦争したのなら殺害された跡の ある骨がたくさんあるはずなのに、それが見つからないということです。確かに、壁画に戦争の図が描かれた時期も、戦死者や戦争被害者の遺骨の年代 も一万二千年前かそれ以降ですから、ネアンデルタール人が消えてから一万年以上あとのことです。けれど、少人数同士の戦いのつみ重ねなら、そんな 遺骨の山が見つからなくても戦争説の否定にはなりません。それよりも、ヨーロッパの研究者は自分たちの先祖が彼らを虐殺したとは思いたくない、そ れが本音だろうと思っていました。
戦争説を採らないのなら、とにかく自滅ということになります。寒さを避け、優勢な他種族との遭遇を嫌ってさ迷ううちに、集団の維持に必要な人数 を割り込んで、日本の野生トキのように絶滅したのでしょうか? 出生率や乳幼児の生存率のわずかな差でも、人口動態には大きな影響を与えます。奈 良貴史さんは、『ヒトはなぜ難産なのか』岩波科学ライブラリー(平成24年)の中で、ネアンデルタール人はヒトより頑丈で頭も大きかったから、そ れだけ余計に難産だったはずだと述べておられます。
ここまできて、ふと『ネ アンデルタール人の正体』の中で片山一道さんが担当された、「地上から消えた人々」を思い出しました。で、そこを読み直 したのです。片山さんは彼らが姿を消した可能性を五つ挙げて、その四番目に、「④はたまた、彼らは獰猛な『殺し屋』クロマニョン人の犠牲になり、 程なく絶滅させられてしまった」と書いていらっしゃるのです。そのうえで、「現在、多くの人類学者たち、ことにヨーロッパやアメリカの人類学者が 信奉するオーソドックス・シナリオなるものは、④の可能性を強調するものばかりです」、とありました。彼は自然人類学や先史人類学がご専門だか ら、そういう分野の国際学会での雰囲気をご存知のはずです。きっと若い世代の研究者たちがそう考えるようになってきたのでしょう。ダーントンの小 説『ネアンデルタール』では、サピエンスが彼らを「だまし討ち」したことになっていました。
彼らが二万数千年前までジブラルタルの洞窟で生きていたことを、僕はネアンデルタール人が、寒気とサピエンス、その両方との闘いを避けたのだと 解釈します。四、五万年前のパレスチナ地方での出合い以来サピエンスの優位を認めた彼らは、このよそ者との争いを避け続けたのだと思います。ここ でアルスアガの本の末尾に置かれた「追悼のことば」から、最後の一行を引き写して連載を終了したいと思います。
「どうか、やすらかにお休みください。(Sit tibi terra levis.)」
平成二十四年十月二十一日